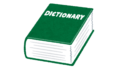RAID(Redundant Array of Independent Disks)は、複数のハードディスクドライブ(HDD)を組み合わせて1つのストレージシステムとして利用する技術です。以下に、各RAIDレベルの仕組み、メリット、デメリットを詳しく説明します。
RAID 0
仕組み:
ストライピングと呼ばれる手法で、データを複数のディスクに分散して書き込みます。最低2台のディスクが必要です。
メリット:
- 読み書き速度が高速。
- 全ディスクの容量を最大限に利用可能。
デメリット:
- 冗長性がなく、1台のディスクが故障すると全データが失われる。
RAID 1
仕組み:
ミラーリングと呼ばれる手法で、同じデータを複数のディスクに書き込みます。最低2台のディスクが必要です。
メリット:
- 高いデータ保護能力。1台のディスクが故障してもデータが失われない。
- 読み取り速度が向上。
デメリット:
- 使用可能な容量が半減する。
- 書き込み速度が低下することがある。
RAID 2
仕組み:
データをビット単位で分割し、エラー訂正コード(ECC)を使用してデータの整合性を保ちます。最低5台のディスクが必要です。
メリット:
- 高度なエラー訂正能力。
デメリット:
- 実用性が低く、コストが高い。
- 書き込み速度が遅い。
RAID 3
仕組み:
データをバイト単位で分割し、専用のパリティディスクを使用してデータの冗長性を確保します。最低3台のディスクが必要です。
メリット:
- 高速な連続データ転送。
- 1台のディスクが故障してもデータを復元可能。
デメリット:
- パリティディスクがボトルネックとなり、書き込みパフォーマンスが低下する。
RAID 4
仕組み:
データをブロック単位で分割し、専用のパリティディスクにエラー検出と訂正のための情報を保持します。最低3台のディスクが必要です。
メリット:
- 高速な読み取り性能。
- データ保護機能。
デメリット:
- 書き込み性能の低下。
- パリティディスクが単一障害点となる。
RAID 5
仕組み:
データとパリティ情報を複数のディスクに分散して保存します。最低3台のディスクが必要です。
メリット:
- 1台のディスクが故障してもデータを復元可能。
- 読み書き速度の高速化。
デメリット:
- 2台以上のディスクが故障するとデータが失われる。
- 書き込みパフォーマンスの低下。
RAID 6
仕組み:
RAID 5の拡張版で、2つのパリティ情報を使用してデータの冗長性を確保します。最低4台のディスクが必要です。
メリット:
- 2台のディスクが同時に故障してもデータを復元可能。
- 高い耐障害性。
デメリット:
- 書き込みパフォーマンスの低下。
- 実効容量が減少する。
RAID 10
仕組み:
RAID 1とRAID 0を組み合わせたもので、ミラーリングとストライピングの両方を使用します。最低4台のディスクが必要です。
メリット:
- 高速な読み書き性能。
- 高い耐障害性。
デメリット:
- コストが高い。
- 実効容量が半減する。
RAIDの各レベルにはそれぞれの特徴があり、用途やニーズに応じて最適なものを選ぶことが重要です。