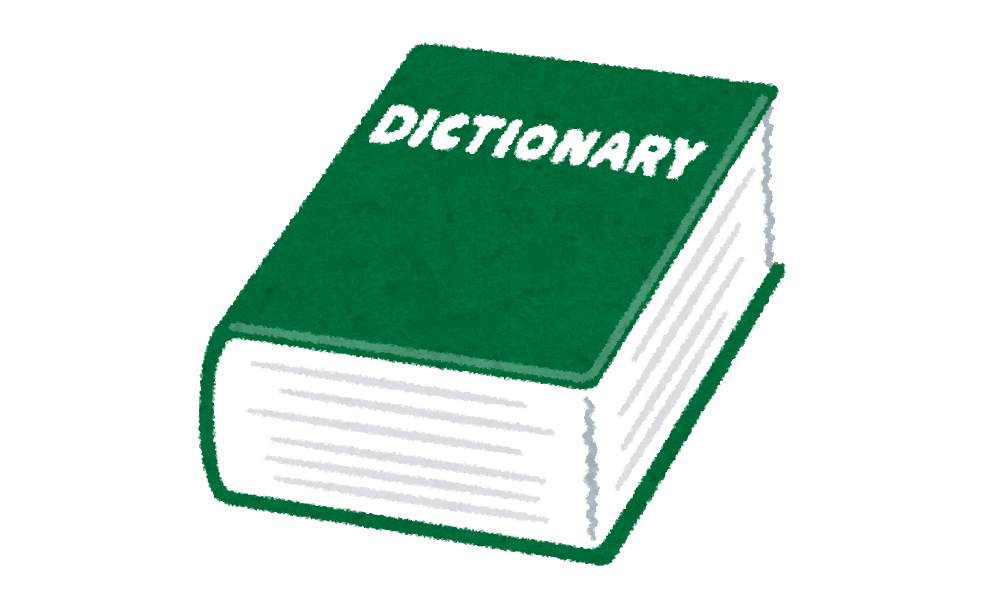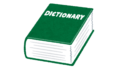仕組み
フラッシュメモリは、不揮発性の半導体メモリで、電源を切ってもデータが保持される特徴があります。主にNAND型とNOR型の2種類があります。
基本構造
フラッシュメモリの基本構造は、以下のような要素で構成されています:
- トンネル酸化膜:数nmの薄い酸化膜で、書き込み時に電荷を蓄積する役割を持ちます。
- 浮遊ゲート:電荷を蓄積するゲートで、電荷の有無がメモリの0と1に対応します。
- 絶縁膜:ゲート電極と浮遊ゲートを絶縁する酸化膜です。
- 制御ゲート:電圧を印加することで浮遊電荷を集める電極です。
動作原理
- 書き込み:浮遊ゲートに電荷を蓄積することで0を書き込みます。
- 消去:浮遊ゲートの電荷を抜くことで1を消去します。
- 読み出し:制御ゲートに正電圧を印加し、ソース・ドレイン間電流の大きさを検出して0と1を判断します。
フラッシュメモリ製品の変遷と歴史
1980年代
- 発明:1980年代に東芝の舛岡富士雄氏がNOR型フラッシュメモリを発明し、1984年に基本動作メカニズムを発表しました。
- NAND型フラッシュメモリ:1987年に舛岡氏がNAND型フラッシュメモリを発明し、1989年に4Mbit NANDフラッシュの試作成功を発表しました。
1990年代
- 製品化:1991年に東芝が世界で初めてNANDフラッシュを製品化しました。1990年代の終わりには256Mbitへと容量が増大しました。
- デジタルカメラ:1990年代にはデジタルカメラでNANDフラッシュが使われ始めました。
2000年代
- 多値技術:2001年に東芝が2bit/セル(MLC)を採用した1Gbit NANDフラッシュを商品化しました。その後、TLC(3bit/セル)、QLC(4bit/セル)へと発展しました。
- 携帯音楽プレーヤー:2005年にAppleが発売したiPod shuffleにNANDフラッシュが搭載され、携帯音楽プレーヤーが普及しました。
2010年代
3D NAND:2014年にSamsungが1チップで容量128Gbitの3D NANDチップを発表しました。3D NAND技術により、大容量化が進みました。
フラッシュメモリは、技術革新とともに容量が増大し、さまざまなデバイスに搭載されるようになりました。これにより、私たちの生活が大きく変わりました。
代表的な製品
フラッシュメモリの代表的な製品には、以下のようなものがあります。
1. USBメモリ
- 概要:パソコンのUSBポートに差し込んでデータを転送する小型の記録媒体です。持ち運びが容易で、データの読み書きが高速です。
- 使用例:データのバックアップや持ち運びに使用されます。
2. SDカード
- 概要:デジタルカメラやスマートフォン、携帯用オーディオ機器などで使用される薄く小さなチップ状の記録装置です。
- 使用例:写真や動画の保存に使用されます。
- 種類:SDカード、miniSDカード、microSDカードなど。
3. SSD(ソリッドステートドライブ)
- 概要:フラッシュメモリを活用した大容量のストレージデバイスで、主にパソコンの記録装置として使用されます。HDDに比べて読み書き速度が非常に高速です。
- 使用例:パソコンのOSやアプリケーションのインストール、データの保存に使用されます。
4. コンパクトフラッシュ(CFカード)
- 概要:デジタルカメラやデジタルビデオカメラで使用されるフラッシュメモリカードです。耐久性が高く、プロフェッショナルな用途にも適しています。
- 使用例:高解像度の写真や動画の保存に使用されます。
5. CFexpress
- 概要:コンパクトフラッシュの後継規格で、さらに高速なデータ転送が可能です。主にプロフェッショナルな映像機器で使用されます。
- 使用例:高解像度の動画撮影や高速連写に使用されます。
6. XQDカード
- 概要:高性能なデジタルカメラで使用されるフラッシュメモリカードで、データ転送速度が非常に高速です。
- 使用例:スポーツや報道写真の撮影に使用されます。
7. CFastカード
- 概要:コンパクトフラッシュの改良版で、高速なデータ転送が可能です。主にビデオカメラで使用されます。
- 使用例:4K動画の撮影に使用されます。
これらの製品は、フラッシュメモリの技術を活用しており、さまざまな用途で広く利用されています。