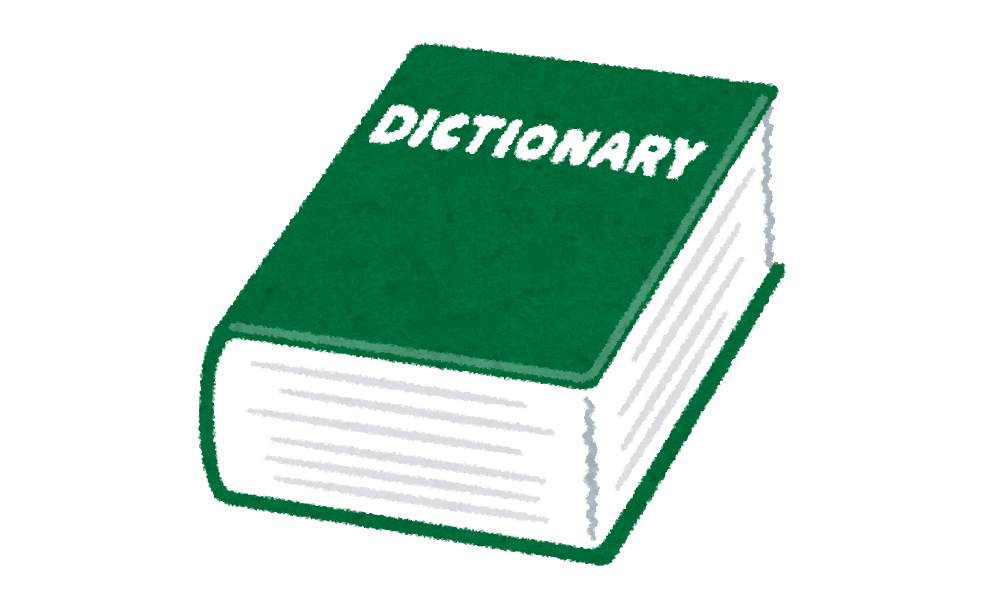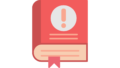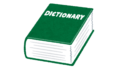ムーアの法則(Moore's Law)は、半導体業界における重要な経験則で、1965年にインテルの共同創業者であるゴードン・ムーアによって提唱されました。この法則は、集積回路(IC)上のトランジスタ数が約18~24ヶ月ごとに倍増するというものです。
ムーアの法則の背景
ゴードン・ムーアは、1965年に発表した論文で、集積回路のトランジスタ数が毎年2倍になると予測しました。1975年には、この予測を2年ごとに2倍になるように修正しました。この法則は、半導体技術の進化を予測する指標として広く受け入れられ、半導体業界の技術開発の目標となりました。
ムーアの法則の影響
- 技術革新の加速:半導体企業は、2年ごとに集積度を2倍にする目標に向けて技術開発を進めました。これにより、微細化技術が急速に進歩し、高性能な半導体製品が次々と生み出されました。
- 製品の小型化・高性能化・低電力化:トランジスタの微細化により、電子機器は小型化しながらも高性能化し、消費電力も低減されました。
ムーアの法則の限界
近年、ムーアの法則のペースを維持することが難しくなってきています。トランジスタのサイズが物理的限界に近づき、従来のスケーリング則に沿った性能向上が限界に達しつつあるためです。そのため、新しい技術開発の方向性として「モア・ムーア」と「モア・ザン・ムーア」が議論されています。
- モア・ムーア:新素材や新構造を導入し、従来の半導体の集積化を継続して高速・高機能化を目指す。
- モア・ザン・ムーア:微細化・集積化に頼らず、半導体チップに新機能を追加・融合することで性能向上を目指す。
ムーアの法則は、半導体技術の進化を支える重要な概念であり、私たちが高性能な電子機器を手頃な価格で利用できるようにする上で大きな役割を果たしてきました。