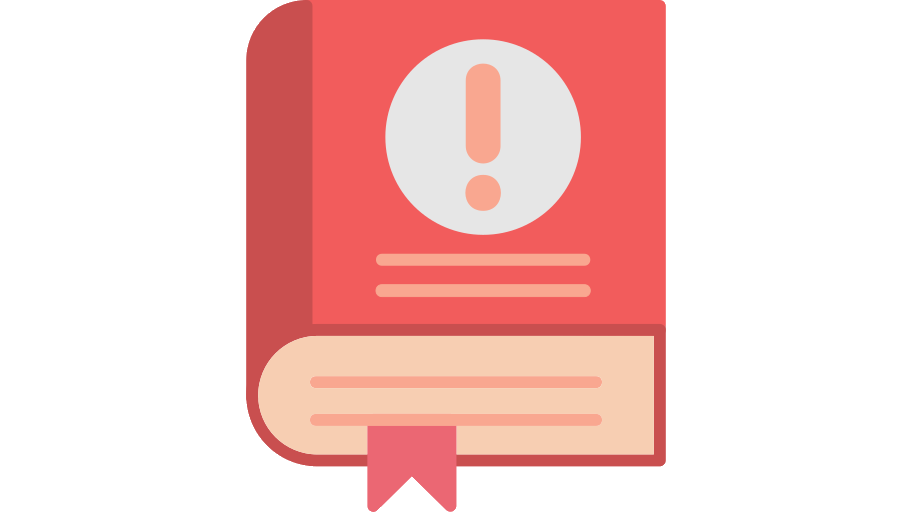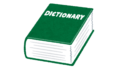標本化定理(サンプリング定理)は、アナログ信号をデジタル信号に変換する際に、元の信号を正確に再現するために必要なサンプリング周波数を示す重要な定理です。この定理は、信号処理やデジタル通信の基礎として広く利用されています。
標本化定理の内容
- 定理の主張: 元の信号を正確に再現するためには、サンプリング周波数が信号の最大周波数(帯域幅)の2倍以上である必要があります。
- この「2倍の周波数」を「ナイキスト周波数」と呼びます。
- 例えば、最大周波数が5kHzの信号をデジタル化する場合、サンプリング周波数は10kHz以上でなければなりません。
応用例
- 音楽CD: サンプリング周波数は44.1kHzで、人間の可聴域(約20kHz)をカバーしています。
- デジタル通信: データの正確な伝送と復元を保証するために、この定理が活用されています。
エイリアシング(折り返し歪み)
- サンプリング周波数がナイキスト周波数未満の場合、元の信号を正確に再現できず、偽の周波数成分(エイリアシング)が発生します。
- この問題を防ぐために、サンプリング前にローパスフィルタを使用して高周波成分を除去します。
標本化定理は、デジタル信号処理の基礎を理解する上で欠かせない概念です。