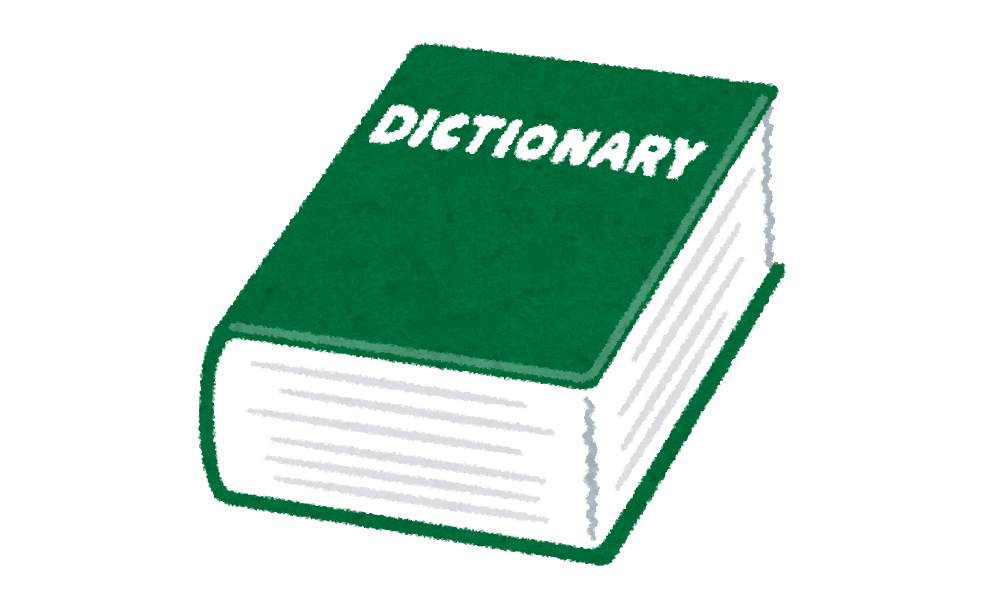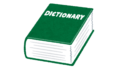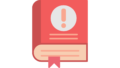ゲーム理論は、複数の意思決定主体(プレイヤー)が関与する状況で、それぞれの行動が他者の行動に影響を与える場合の意思決定を分析する学問です。この理論は、経済学、政治学、心理学、計算機科学など、さまざまな分野で応用されています。
ゲーム理論の基本概念
- プレイヤー:
- 意思決定を行う主体。個人、企業、国家などが該当します。
- 戦略:
- プレイヤーが選択できる行動の集合。例えば、価格設定や広告戦略など。
- 利得:
- プレイヤーが特定の戦略を選択した結果得られる利益や評価。
- ゲームの種類:
- 協力ゲーム(プレイヤー間で合意が可能)。
- 非協力ゲーム(プレイヤーが独立して行動)。
ゲーム理論の代表的なモデル
- 囚人のジレンマ:
- 2人の囚人が「協力」か「裏切り」を選択する状況。
- 両者が裏切る状態がナッシュ均衡となり、全体として非効率的な結果を招く。
- ナッシュ均衡:
- 各プレイヤーが他者の戦略を考慮した上で、自分の戦略を変更するインセンティブがない状態。
- ゼロサムゲーム:
- 一方の利得が他方の損失となるゲーム。例: チェスやポーカー。
- 協力ゲーム:
- プレイヤー間で拘束力のある合意が可能な状況。例: 企業間の共同事業。
ゲーム理論の応用例
- 経済学: 市場競争や価格設定の分析。
- 政治学: 国際関係や政策決定のシミュレーション。
- 環境問題: 資源の分配や環境保護の戦略。
- 日常生活: 家庭内の役割分担や交通渋滞の分析。
ゲーム理論は、合理的な意思決定を理解するための強力なツールです。