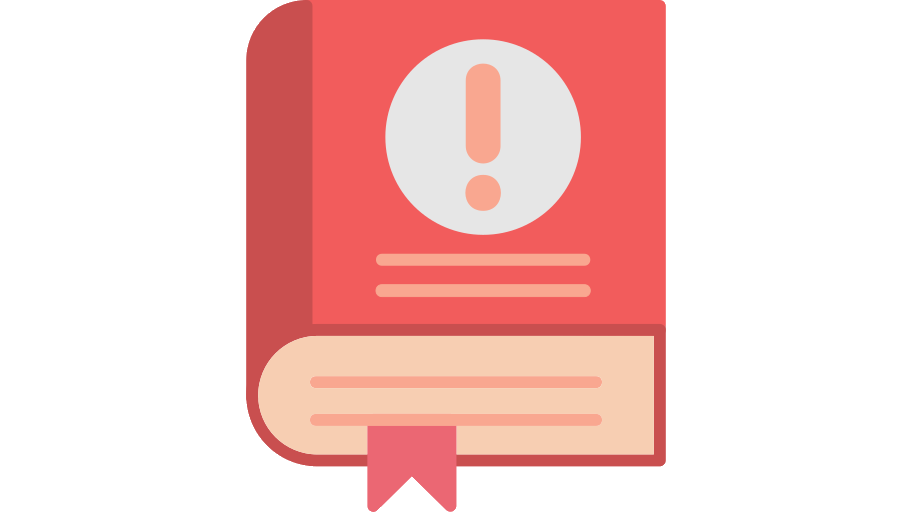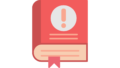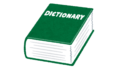マイナンバー法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は、個人番号(マイナンバー)を利用して、行政手続の効率化や国民の利便性向上を図るための法律です。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
経緯
マイナンバー法は、2013年に成立し、2016年1月から施行されました。この法律は、行政手続の簡素化や効率化を目的としており、国民一人ひとりに12桁の個人番号が付与されます。これにより、複数の行政機関が保有する個人情報を一元的に管理し、情報の連携を図ることができます。
法律の主な条項
- 目的(第1条):
- 個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受を図ることを目的としています。
- 個人番号の指定と通知(第4条、第5条):
- 市町村長は、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、書面により通知します。
- 個人番号の利用範囲(第6条):
- 個人番号は、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。具体的には、年金、雇用保険、医療保険、福祉、税務などの手続きに使用されます。
- 特定個人情報の保護(第14条 - 第30条):
- 特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の適切な管理のための措置を講じることが求められます。
- 個人番号情報保護委員会の設置(第31条 - 第51条):
- 個人番号情報保護委員会は、特定個人情報の取扱いに関する監視や監督を行います。
法律が適用される事例
- 年金の手続き:
- 年金の資格取得や確認、給付の手続きにおいて、マイナンバーが利用されます。
- 税務申告:
- 確定申告書や届出書にマイナンバーを記載することで、税務手続きが簡素化されます。
- 災害対策:
- 被災者生活再建支援金の支給など、災害対策に関する手続きにおいてもマイナンバーが利用されます。
- 福祉サービスの利用:
- 児童手当や生活保護などの福祉サービスの申請時に、マイナンバーが必要となります。